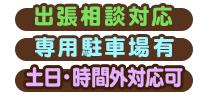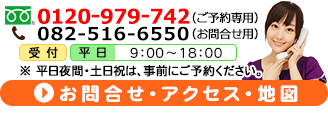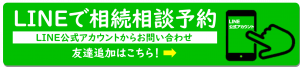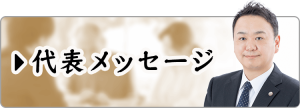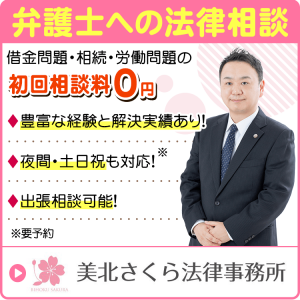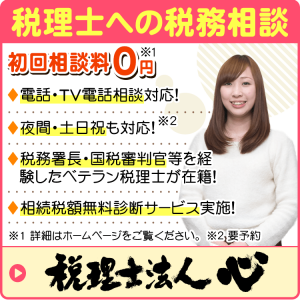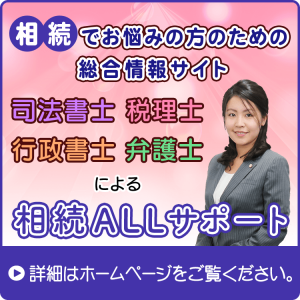遺産分割協議とは? その進め方について(具体的相続分を決める)
1 はじめに


『遺産分割協議』の進め方について基本的な内容のご紹介をさせていただきたいと思います。
『遺産分割協議』をおこなう前提としては、
④ 具体的相続分を決める。
があげられます(以前の記事もそれぞれご参照ください。)。
今回は、「④具体的相続分を決める」についてご紹介いたします。
2 「法定相続分」について
「④具体的相続分を決める」にあたっては、遺言がない場合、法定相続分(民法900条)を基本にして進めることになります。
法定相続人全員の了承があれば、法定相続分に縛られず自由に相続財産の分配・取得を決めることができます。
<法定相続分>
相続人:①配偶者:1/2と子(代襲相続人・孫):1/2
②配偶者:2/3と直系尊属(親、祖父母):1/3
③配偶者:3/4と兄弟姉妹」1/4
となります。
● 配偶者がいない場合には、①②③それぞれ配偶者以外の相続人が取得します。
● お子さんが数人ある場合は、ひとしく相続分を有します。
● 兄弟姉妹が数人ある場合も、ひとしく相続分を有します。
● 婚内子と婚外子で、法定相続分に違いはありません。
● 代襲相続人がいる場合、被代襲者が受けるべきであった相続分を900条4号によって相続分を有することになります。
3 「法定相続分」に修正が加わる要素
⑴ 遺産分割において、法定相続分で協議を進める際、「遺贈」や「生前贈与」等の『特別受益』がある場合、『特別受益』を相続財産に持戻し、みなし相続財産を算出します。
その上で各相続人の相続分を算定することになります(民法903条1項)。
⑵ 相続人に対して、生前に一定の寄与をした相続人がいた場合、その相続人が『寄与分』を考慮して欲しいと求める場合には、寄与分を決めた上で法定相続分を修正をすることもあります(民法904条の2)。
⑶ 「相続放棄」や「相続分の放棄」によっても相続分は変動します。
4 さいごに
遺産分割協議において、「具体的相続分を決める」ことは大いに問題となります。
実家に同居した子が「自分が多く遺産をもらうべき」だと主張することは、遺産分割協議の中でも頻回の問題です。
そうした場合、「法定相続分」をベースにしながら、相続人間で「『特別受益』、『寄与分』として法的に認められるか?」、「このぐらいは譲ろう。」などの協議が行なわれます。
『遺産分割協議』にあたっても、相続案件にも慣れた弁護士にご相談をされることをオススメいたします。
受付時間
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
平日:9:00~18:00
定休日:土日祝
※ご予約の上、土日及び営業時間外の対応も承っております。
所在地
〒731-0221広島県広島市安佐北区
可部3丁目19-19
佐々木ビル(南棟)2階
可部街道沿い、広島市安佐北区総合福祉センター隣、上市バス停すぐそば、サンリブ前、もみじ銀行可部支店前
※ 駐車場は、福祉センター裏手にございます。
0120-979-742